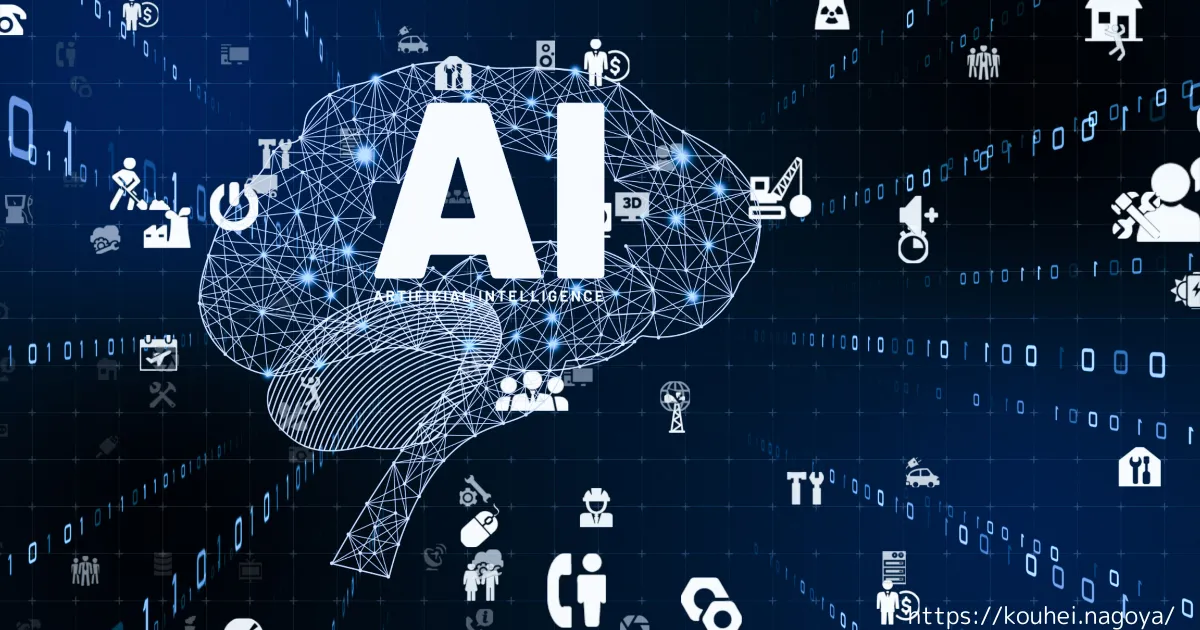トランプ関税ショックで世界中が騒然となっています。今日の東京市場も3万1千円割れの局面がありました。トランプ関税ショックの影響は、今後の海外市場も含めてもう少し見極めたいと思います。一方、トランプ騒動のおかげで年初の中国製生成AIディープシーク・ショックの影が薄くなりましたが、こちらの方も目が離せません。今年は国際情勢も含めて、投資家には悩ましい展開になりそうです。
1.ディープシーク・ショック
中国製のディープシーク(DeepSeek、深度求策)が公開されたのは1月下旬。このメルマガでも取り上げました。
OpenAIのChatGPT並みの性能の生成AIを極めて低コストで開発したという触れ込みに世界が驚き、株式市場に大きな影響を与えました。
ディープシークR1及びR1-Zeroがリリースされたのは1月20日ですが、ディープシークが大々的に報じられた直後の1月27日のニューヨーク株式市場に大きな影響を与えました。
先端半導体の輸入制限に晒される中で中国企業ディープシークが高性能の生成AIを開発したことは、先端半導体を使わなくても開発ができること、中国に対する輸出規制が意味をなさないことを世界にアピールし、市場心理に動揺を与えました。
生成AIブームで株価が高騰していたNVIDIA株は1日で約17%下落し、同社の時価総額は約5900億ドル(約91兆円)消失。同日のナスダック市場全体の時価総額は約1兆ドル(約154兆円)以上が消失しました。
逆にディープシークはブームとなり、主要なアプリストアでダウンロードランキング全米1位を獲得。1月下旬から3月上旬にかけて話題を席巻し、世界は「ディープシーク・ショック」の様相を呈しました。
中国政府が成果を積極的にアピールしたこともあり、ディープシークの登場は中国ハイテク株全体を底上げする契機となり、対照的に米ハイテク株は調整局面入り。米ハイテク株から逃げだした資金の一部は、香港に上場する中国ハイテク株にシフトしました。
香港ハンセン・テクノロジー株指数はディープシーク・ショック前の水準から3月6日に付けた直近高値(6068.77ポイント)まで、約1ヶ月半で約35.8%上昇しました。
ディープシークの急成長を受け、OpenAI、Google DeepMind、Anthropic、Metaなどの主要AI企業は、競争力維持と市場の主導権確保のためにさまざまな対抗策を講じています。技術革新、商業展開、オープンソースの推進、規制戦略など、対抗策は多岐にわたります。
第1に技術的な差別化による優位性確保の動きです。OpenAIはGPT-4 TurboやGPT-5への進化を進めており、長文処理や複数モーダル(音声・画像・動画など)の統合など、汎用性の高い機能を強化しています。
Google DeepMindはGeminiシリーズを軸に、検索や生産性ツールとの統合を図り、エンタープライズ市場への浸透を進めています。
第2に、オープンソース戦略を通じて広範な開発者コミュニティの支持を得ようとする動きです。MetaはLLaMAモデルを中心に、誰でも利用・改良できる基盤を整備し、クローズドなモデルとの対比を鮮明にしています。
これにより、ディープシークのようなクローズドモデルとの差別化と、エコシステム全体での技術革新を促進しています。
第3に、価格競争における対抗策として、クラウド基盤の活用やスケーラブルなAPI提供などが進められています。AnthropicはClaudeモデルの廉価提供を進め、中小企業や開発者層へのアプローチを強化しています。これにより、ディープシークの低価格・高性能モデルに対抗しています。
第4に、安全性と倫理性の強調による信頼構築も重要な対抗戦略です。Anthropicは「憲法AI」の概念を掲げ、倫理ガイドラインに基づくモデル訓練を行っていることをアピールしており、企業や行政機関からの支持を集めています。OpenAIも「AIの民主化」と「長期的な安全性」を掲げ、政府との連携を強化しています。
国際的なガバナンス構築に向けた提言活動も活発に行われています。これにより、ディープシークのような中国発のプレイヤーの影響力を抑え、自国の技術優位性を守る枠組みづくりを目指しています。
特に米国・EU圏では、安全性・透明性・倫理性を重視した規制枠組みが模索されており、ディープシークの台頭を警戒する姿勢が色濃く見られます。
2.フェイクキャンペーン
上述のようなディープシークへの対抗策が講じられる背景には、ディープシークに対する不信感が影響しています。
低コストでありながら高スペックを実現した「驚異の最先端AI」として世界の話題を独占したディープシークでしたが、リリース直後から指摘されていたのが「蒸留」疑惑です。
「蒸留」とは、他社のLLMをモデルに学習することで学習プロセスを効率化・簡略化する開発手法であり、他社データへの不正アクセスに繋がる疑惑です。
さらに2月27日、シンガポール当局がシンガポール人2名、中国人1名を、NVIDIA製の最先端半導体を不正に入手・輸出したとして詐欺罪で逮捕・起訴したというニュースが報道されました。
不正に取得・輸出されたNVIDIA製半導体はAIサーバーに搭載され、マレーシア経由で中国のディープシークに渡った可能性が指摘されています。
また、半導体やAIに関する調査・分析を行なう米有力調査会社(セミアナリシス)が、「ディープシークはAI開発のために少なくとも5億ドル相当の半導体を購入し、NVIDIA製半導体のH800を約1万個、H100を約1万個、H20を約3万個保有している」とレポートしました。
この内容が事実であれば、ディープシークが最先端の半導体を使用せず、低コストで高度なAI開発に成功したとする説明は嘘であった蓋然性が高いと言えます。
さらに「ディープフェイク検知サービス」を提供するイスラエルのITセキュリティ企業(サイアブラ社)が「ディープシークの組織的な偽情報キャンペーン」という調査レポートを公表しました。
同レポートの中で、一連のディープシーク・フィーバーが、意図的に作られた数千もの偽アカウントを起点に、中国政府関与の元で組織的かつ大々的に行われた「偽情報キャンペーンであった可能性が高い」と報じています。
ディープシークに関するこうした情報が明らかになるにつれ、当初の「破壊的イノベーション」という評価とは異なり、最先端のAIを追いかける「ファスト・フォロワー(Fast follower、素早い後追いプレーヤーのこと)」に過ぎないとの見方が強まっています。
ディープシークについての疑惑情報が事実であれば、今後の米中のAI開発競争について、AI開発にはやはり巨額の投資や最先端の半導体が必要であり、こうした点で中国を圧倒する米国の優位は変わらないことが推察できます。
以上のディープシークに対する疑問と懸念等について、要点を再整理しておくと以下のとおりです。
第1に、技術的な透明性の欠如。ディープシークは、GPT-4やClaudeと比較されるような高性能モデルを発表していますが、その詳細な訓練データやアーキテクチャ、評価手法などに関する情報は限定的です。学術界やオープンソースコミュニティからは「ブラックボックス的存在」として捉えられ、信頼性が低いのが実情です。
第2に、安全性と倫理的ガバナンスの体制にも疑問が呈されています。生成AIの出力が差別的、偏見的、または虚偽情報を含むことが広く知られています。
その対応には明確なポリシーと検証体制が不可欠ですが、ディープシークがどのような安全対策を講じているのか、公的に明示された情報は少なく、透明性が不足しているとされています。また、中国国内での規制に準拠して運営されている可能性があり、ユーザーの言論の自由やプライバシーへの配慮が十分でないと見られています。
第3に、ディープシークの政治的背景も懸念材料となっています。中国政府との関係性や、国家主導のAI開発戦略の一環としての存在である可能性があるため、欧米諸国の安全保障上の懸念を引き起こしています。
実際、アメリカをはじめとする複数の国では、国産AI開発の支援や中国系AI技術へのアクセス制限などの対策が講じられています。
第4に、産業界への影響も議論の的になっています。ディープシークは価格競争力を武器に急速にシェアを拡大しており、他の企業やスタートアップにとって大きな脅威となっています。とりわけ、低価格で高性能なモデルを提供することで、小規模ベンダーや独立系開発者の競争力を削ぐ可能性があります。
総じて言えるのは、ディープシークの技術力と革新性は高く評価されつつも、その運営体制、倫理的姿勢、政治的リスクなどに関しては慎重な見方が必要でしょう。
もっとも、信頼性が低く、フェイク評価だったとしても、ディープシークが相当レベルの生成AIであることに変わりはなく、中国が生成AI開発に関する人材リソースを蓄積していることは事実であり、中国の実力を侮れないことは言うまでもありません。
3.生成AI開発競争
こうしたディープシーク騒動の中で、生成AIの開発競争はますます激化しており、主要プレイヤーの動きはグローバルな技術・経済・政治の枠組みに大きな影響を与えている。
まず、OpenAIはGPT-4 Turboを中心に高性能なAPIサービスを提供しており、ChatGPTの有料プラン(ChatGPT Plus)では500以上のカスタムGPTが稼働しています。加えて、近日中に発表が期待されているGPT-5では、より強力なマルチモーダル機能、長期的記憶、複雑なタスク処理が可能になるとされており、企業向けSaaSとの統合も進んでいます。Microsoftとの連携も強固で、Azure OpenAI Serviceを通じてエンタープライズ領域を拡大しています。
Google DeepMindはGeminiシリーズを軸に、検索連携、Google Workspace統合、Android端末へのAI搭載といった形で製品へのAI融合を加速しています。Gemini 1.5では、最大100万トークン以上の長文処理が可能とされ、法務、研究、金融など専門性の高い分野での活用が期待されている。
Anthropicは「憲法AI」という独自の倫理的フレームワークを活用し、Claudeシリーズを通じて安全性・透明性・信頼性の高いモデルを展開しています。Claude 3では、高度な推論力とマルチモーダル対応が加わり、OpenAIやGoogleと真っ向から競合しています。また、Amazonと提携し、クラウド提供を強化することで、ディープシークを含む他社モデルに対抗しています。
Meta(旧Facebook)はLLaMAシリーズを中心としたオープンソース戦略を積極展開し、特に研究者・開発者コミュニティへの支持を広げています。LLaMA 3は大規模な多言語データを用いたトレーニングが行われており、翻訳やグローバル対応に強みを持ちます。MetaはAIの民主化とオープンエコシステムの形成に注力しており、クローズド戦略のディープシークやOpenAIとは対照的な立場をとっています。
そのほか、xAI(Elon Musk)やCohere、Mistral、Stability AIなども独自モデルの開発を進めており、それぞれが専門性やオープン性、速度、拡張性などを差別化要因として競争しています。とりわけxAIは、X(旧Twitter)との統合やロボティクスとの連携を視野に入れた「実世界との統合AI」に注力しています。
競合各社の開発競争と並行して、生成AIに対する規制・国際協調の動きも進んでおり、企業戦略に影響を与えています。
EUのAI法、米国のAIに関する大統領令、日本のAIガイドライン等々、各国の法整備が進んでおり、企業はこれに対応した設計やガバナンス対応が求められています。
トランプ関税ショック前までの情報ですが、上述のとおり、AI関連株の代表格ともいうべきNVIDIAは好調な業績が続く一方、株価はディープシーク・ショックを契機に大きく調整に転じたことで、12ヶ月先予想株価収益率(PER)はピーク時の40倍超の水準から20倍台半ばまで低下しました。
NVIDIAの業績は力強い増益トレンドが続いていることもあって、同社のPEGレシオ(今期予想PERを今期の一株当たり利益EPS成長率で割った数字)は約0.9倍にとどまり、S&P500種指数の約1.5倍(今期予想PER約20.9倍、今期EPS成長率約14.1%、いずれも3月末段階)を大きく下回る水準となっています。
トランプ関税ショック後の動きは改めて分析する必要がありますが、当分の間、NVIDIAが生成AI相場の中心であることに変わりはなさそうです。
ディープシークのフェイクキャンペーンが事実であるとすれば、第2幕、第3幕も十分に想定されます。投資家としては、どのようなニュースに、どのような反応をするか、トランプ関税ショックも加わって、今年は舵取りが難しい年になりました。(了)