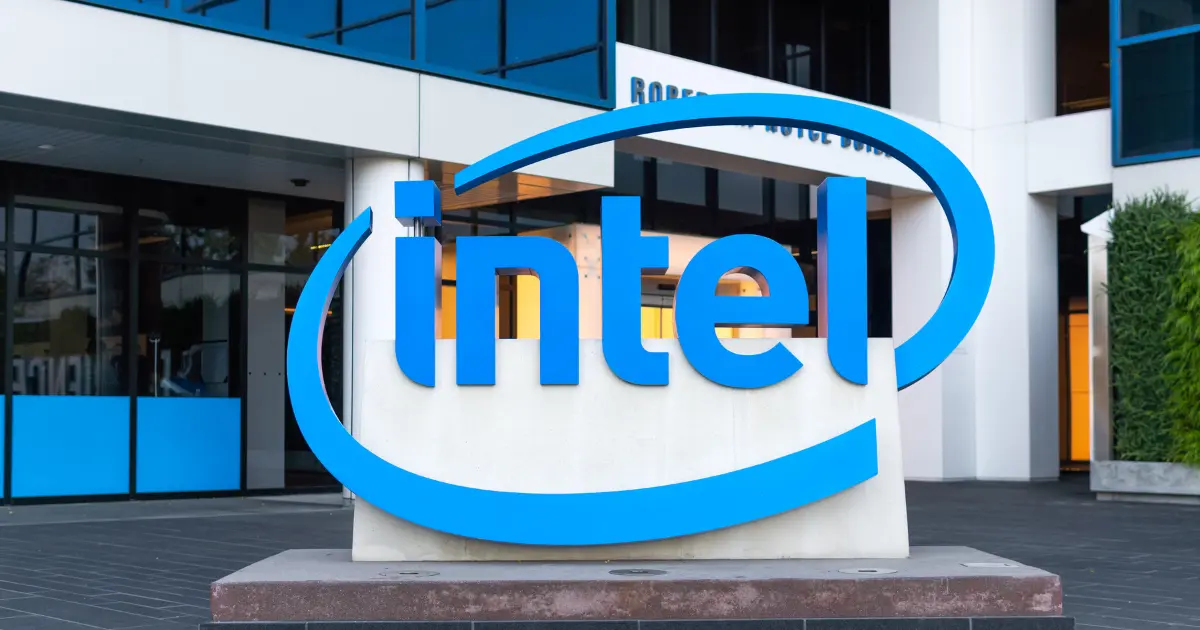韓国の戒厳令には驚きました。それが国会で議決されて一晩で解除されたのにも驚きました。韓国の過去の戒厳令は大統領が軍人出身の場合がほとんどですから、文官出身の尹大統領が発令したのにも驚きました。さらに、発令の理由が国会と国政の停滞ということにも驚きました。韓国情勢に気をとられていたら、今度はフランスで内閣不信任案が可決されました。新年早々発足の米トランプ新政権の対中強硬姿勢を含め、世界は混沌の度合いを深めています。そのうえ、政治と経済の混交も深みを増しており、今や「地政学」ではなく「地政経学」という視座が不可欠の時代になりました。
1.インテルCEO退任
米インテルは12月2日、パット・ゲルシンガーCEO(最高経営責任者)の退任を発表しました。ゲルシンガー氏の経営手腕に対する不信感が高まった結果です。
暫定会長に就いたフランク・イアリー氏は「よりスリムでシンプルで機敏なインテルを作るべく取り組んでいる」とコメントしています。
ゲルシンガー氏は1979年から約30年間インテルに勤務し、初のCTO(最高技術責任者)に就任。2009年から米EMC(電子機器企業)でCOO(最高執行責任者)、社長を歴任、2012年にVMware(半導体企業)CEOに転身、2021年にボブ・スワン氏の後任としてインテルCEOに就任しました。
ゲルシンガー氏はCEOとして、台湾TSMCや韓国サムスン等の半導体大手に対抗し、複数の大規模工場を建設。CHIPS法(半導体強化法<後述>)の下、米連邦政府から補助金も獲得しました。
詳細は後述しますが、CHIPS法は2022年8月に成立した法律です。同法によって、今後5年間で国内の基礎研究費に約2000億ドル、半導体製造能力強化に約527億ドルを充てる内容です。合計約2800億ドルに及ぶ大型予算は、中国との競争、安全保障対策を見据えたものです。
ゲルシンガー氏の在任中、PC向けチップ収益は減少し、AI向け製品でもNVIDIA等の後塵を拝しました。また、ソニーとのチップ設計・製造契約にも失敗しました。
インテルの売上高は2023年のゲルシンガー氏CEO就任時から約3分の1に減少。2024年第2四半期には約1万5000人の人員削減を発表し、第3四半期は3期連続の赤字となり、同社として四半期ベースでは過去最大166億3900万ドルの赤字を計上。
巨額赤字の原因は設備の減損損失やリストラに伴う費用計上です。コロナ禍特需を見込んで過剰投資した旧世代半導体製造設備で約31億ドルの減損を計上したほか、2017年に買収した自動車向け半導体子会社モービルアイの暖簾(のれん)代償却、繰り延べ税金資産取り崩し約99億ドル、リストラ関連で約185億ドル等の費用計上です。
ゲルシンガー氏としては生産体制強化のための決断であり「構造改革の非常に困難な時期を乗り越えた。将来に向けて準備ができた」とコメントしていました。インテルは9月末時点の自己資本は1000億ドル超え、総資産で割った自己資本比率は54%の優良財務体質であり、次期四半期は人件費削減等の効果で一時的に業績が回復する見通しです。
こうした動きを好感して、四半期決算発表直後の米株式市場時間外取引でインテル株は同日終値に比べ一時約15%上昇。ゲルシンガー氏が自社の構造改革に目途を付けて攻勢に出る構えを示した矢先の退任劇です。
その背景には、インテルが技術的な窮地に立っていることが影響していると思います。微細化技術は競合他社に出遅れ、競争力低下は牙城としてきたCPU分野に及んでいます。
インテルが強みとしてきたPCやサーバー向けCPUでは、米マイクロソフトとともに「ウィンテル」時代を築き、一世を風靡してきました。
しかし、インテルは半導体の設計と生産で分業体制が進む潮流を読み切れませんでした。設計と生産の両方を手掛ける垂直統合モデルに長年こだわった日本の半導体メーカーと似ています。
今から37年前の1987年、台湾政府主導でTSMCが設立された当初、TSMCの事実上の創業者モーリス・チャン(張忠謀)氏がインテルに資金支援を依頼しました。
その際、モーリス・チャンが目指すファウンドリー方式(設計と生産の分離、受託生産特化、水平分業)のビジネスモデルをインテル側は評価せず、出資を断ったそうです。
以後、TSMCは幅広い企業から先端半導体の生産を請負い、技術力とノウハウを蓄積。一方、インテルは設計と生産の垂直統合方式で自社製だけを手掛け、1990年代から2000年代半ばまでは「インテル入っている」というコマーシャルに象徴される全盛期を築きました。
しかし、2010年代以降の微細化等の加速局面で明暗が分かれ始めました。インテルは2019年時点でCPU市場でシェア90%を誇っていましたが、2023年には64%まで低下。一方、TSMCは躍進し、今や世界の半導体生産を牛耳っています。
ゲルシンガー氏は遅れを挽回しようと、受託生産を手掛ける体制整備に乗り出し、米政府の補助金を梃子に、先端半導体の生産能力を増強する戦略に打って出たものの、今回の退任劇となりました。
2.AMD台頭
同じ期間に市場シェアを9%から24%まで伸ばしたのがインテルのライバル的地位になりつつあった米AMD(アドバンスト・マイクロ・デバイス)です。データセンター向けCPUに限ればAMDは約35%までシェアを伸ばしています。先端品の性能では既にAMDがインテルを上回っているという評価も聞きます。
このメルマガでも過去に取り上げていますが、AMDは1969年、フェアチャイルドセミコンダクターを退社したジェリー・サンダース等がカリフォルニア州サンタクララに設立。インテルのセカンドソース(OEM生産や類似品生産)企業として活動する一方、自社製の64ビット対応マイクロプロセッサ、APU (Accelerated Processing Unit)、GPU (画像処理半導体)、フラッシュメモリ等を生産してきました。
黎明期からAMD独自設計のFPU(Floating Point Unit、浮動小数点演算処理装置)等で事実上の標準(デファクトスタンダード)を獲得し、逆にインテルがセカンドソース製品を生産したり、インテルのセカンドソース製品でありながらインテル製よりも高性能のDMA(Direct Memory Access、直接アクセスメモリ)コントローラを開発する等々、技術力の高さでは独特の存在感を示していました。
つまり、AMDは基本的にはインテル全盛期のセカンドソースメーカーのひとつでしたが、知る人ぞ知る企業として命脈を保ち、地味ながらも独特の存在感を維持してきました。
そうした中、インテルは1985年発表の「Intel 386プロセッサ」以降、セカンドソースを認めず、製造に必要な重要資料を公開しない方針に転換。つまり、独占純化路線に転じました。
多くのセカンドソースメーカーは撤退しましたが、AMDを含む数社は独自開発を行い、同一ではないもののインテル製と互換性のあるプロセッサを生産し続けました。
AMDはPCやサーバー向けCPUでインテルとシェアを競いつつ、2006年に加ATIテクノロジーズを買収してGPUに参入。ゲーム向け等の事業にも進出しました。
2012年、このメルマガでも紹介したとおり、NVIDIA製のGPUが世界の注目を集めます。同年のAIコンテストで加トロント大学がNVIDIA製GPUを使用して圧勝したことが契機です。
その間もAMDはAIの可能性に着目し、AI向けGPUの開発を続けていたほか、開発用CPUも手掛けていました。それが上記(この項の冒頭)のデータセンター用CPUです。
2022年に米新興オープンAIがチャットGPTをリリースすると、生成AIそのものとともに開発用CPUがブームになっています。
こうしてAMDは、生成AIの処理に必須のGPUに加え、開発用CPUでも上昇気流に乗りました。インテルの今年第3四半期のデータセンター向け事業売上高が前期比9%増の33.5億ドルであったのに対し、AMDは同2.2倍の35.5億ドル。この分野で順位が入れ替わりました。
両社の明暗を分けたのはビジネスモデルの違いです。AMDは経営不振に陥った2009年3月に生産部門をグローバルファウンドリーズ社として分社化。水平分業体制を選択しました。本体は開発と設計に特化、生産はTSMCに委託し、復活を遂げました。
一方、設計と生産の垂直統合体制にこだわったインテルは2019年頃からTSMCに微細化技術で差をつけられ始めました。半導体回路の微細加工に使うEUV(極端紫外線露光装置)導入でも後手に回り、TSMCとタッグを組んだAMDに先端品シェアを奪われる事態に至っています。
そして今回のAMDとインテルの逆転。AMDは単にインテルを逆転しただけでなく、NVIDIAの対抗馬として浮上しています。
2023年に生成AI向けGPU「MI300」を投入。トランジスタ数は1530億個と、技術面ではNVIDIA製に劣らないそうです。リサ・スーCEOは「AMD史上最も急成長した製品」と称しています。
インテルは半導体の開発から生産を一貫して手がける米国唯一の大手企業です。半導体の自国調達比率を高めるため、米政府は3月にインテルに最大85億ドルの補助金支出を決定。9月にも最大30億ドルの追加支出を決定。
インテルの競争力の帰趨は、米政府の経済安全保障戦略、CHIPS法の成否にも影響します。目が離せません。
3.CHIPS法
上述の米国CHIPS法(正式にはCHIPS and Science Act of 2022)は一昨年8月に成立しました。同法は中国を念頭に米国の競争力強化のために総額2800億ドル(約42兆円)を先端技術研究開発に投資するものです。半導体生産支援527億ドル(約8兆円)の資金援助(補助金)も含まれています。
CHIPS 法を念頭に、米国テキサス・インスツルメンツ、インテル、マイクロン、韓国のサムスン電子等が相次いで米国に新たな先端半導体工場設立を表明。台湾TSMCもアリゾナ州でアップル向け等の工場を建設中。各社とも米国政府の資金援助を念頭に置いています。
商務省は傘下の国立標準技術研究所(NIST)内に「CHIPSプログラム室」を設置し、資金援助の仕組みや「ガードレール条項」の内容を検討。昨年9月25日にガードレール条項の案が発表され、11月24日より以下の内容が施行されました。
資金援助を受けた企業は10年間、中国を含む「懸念国」での半導体生産能力拡張を制限されます。具体的には、先端半導体施設の場合、既存施設能力拡張を伴う10万ドル以上の取引禁止、既存施設能力5%以上向上を目指す投資禁止。レガシー半導体施設の場合、既存施設能力10%以上向上を目指す投資禁止。製造施設建設はチップの85%以上が懸念国内で消費される場合に限定。安全保障上懸念のある技術や製品に関して、懸念国団体との共同研究や技術ライセンス供与契約締結禁止等々です。
以上のように、CHIPS法は経済と安全保障の側面を持っており、西側半導体企業はその狭間で如何に立ち回るかが問われています。
CHIPS法は米国半導体業界を代表するロビイング組織である米半導体産業協会(SIA)が2020 年9月に発行した報告書「半導体製造における政府インセンティブと米国の競争力」が基になっています。
同報告書の主張は大きく3点です。第1は、米国が強い国内半導体生産力を持つことが今後数10年間の安全保障と経済競争力を決定する「戦略的技術」に影響を与えること。
その戦略的技術として、5G、量子コンピューティング、AI、自律システム、宇宙極超音速、サイバーセキュリティを挙げています。
第2は、米国の世界における半導体生産シェアが過去数10年間に急落、一方で中国等の競争相手国は補助金政策によりシェアを上昇させていると指摘。具体的には1990 年の世界における米国シェアは37%でしたが、2020年見通し(報告書公表時点)12%、2030 年10%となる見通しを示しました。
一方、中国の1990年の世界シェアは0%でしたが、2020年見通しでは15%と米国を逆転。2030年には24%と予想。中国躍進の主因が1000億ドル超の補助金政策であるのに対し、米国は補助金政策を行っていないと指摘。
上記2点を踏まえ、第3に米国も200億ドルから500 億ドル相当の補助金政策を行うべきと主張。例えば、500億ドルの補助金政策によって新たに19の半導体工場稼働を予想(報告書公表時点の実稼働半導体工場数は全米で70)。その結果、2030年には中国には及ばないものの世界2位の半導体生産国の地位を維持すると予想しています。
SIAによるロビイング活動等が奏効し、2021年1月に2021 年度国防権限法(NDAA)の中に「CHIPS for America Act」が盛り込まれて成立。同法9901条から9908条がCHIPS法の規定に該当し、同条文により国内半導体製造に対する連邦資金付与が認められました。その後、上述のとおり2022年8月にCHIPS法が成立。
CHIPS法はDivision AとDivision Bの2 章構成です。Division Aでは、半導体関連に5年間で527億ドル(5G通信網オープン化のための15億ドルを含めると542億ドル)の予算を割り当てることを明記。Division Aには税額控除240億ドルの歳出も含まれています。
Division Bは国立科学財団(NSF)等の米国政府各研究機関向けに今後10年間の研究開発予算支出を明記(歳出授権)。具体的金額は今後別の法律で決めます。
SIAによるとCHIPS法案が連邦議会に提出された2020年からCHIPS法成立数ヶ月後までの約2年半に関係各社が発表した今後10年間の米国内新規投資計画(新規工場建設や既設工場拡張等)総合計は約2000億ドル。直接新規雇用約4万人、間接新規雇用を含めると数10万人の雇用創出を予想。いずれも米国政府の資金援助を想定しての動きです。
上述の国防権限法9902条には「商務省は半導体の製造、組立、検査、先端パッケージング、または研究開発に関する米国内の施設や装置への投資を促すために、資金援助プログラムを立ち上げる」と明記。毎年度国防予算の大枠を定める国防授権法の中に半導体産業振興が盛り込まれました。半導体産業が国防と密接に関わっていることを意味します。
約527億ドルの内訳は「先端ロジック及びメモリー半導体の国内生産の確立」約280億ドル、「現世代及びレガシー半導体の国内生産の確立」約100億ドル、「半導体の研究開発における米国のリーダーシップの強化」約110億ドル等。先端半導体だけでなく、コロナ禍で供給不足が露呈したレガシー半導体も重視されていることがわかります。
商務省は昨年2月28日、第1弾の資金援助申請受付開始を発表。その際、今後10年の達成目標を掲げました。第1に最低2ヶ所の先端ロジック半導体の大規模クラスター形成、第2に複数の先端パッケージング量産施設建設、第3に先端メモリー半導体(DRAM)量産、第4に現世代及びレガシー半導体の生産能力向上です。
商務省はまた「安全保障」「商業的可能性」「財務健全性」「プロジェクトの技術的実現可能性とその覚悟」「労働力開発」「より大きなインパクト」を重視して審査を行う旨も表明。
例えば「財務健全性」では、申請者は州または地方自治体から資金援助を得られる者であることが条件。つまり、地域から信頼を得ている企業であることが前提です。
「労働力開発」では、地元教育機関と連携した施設従業員向け研修プログラム実施を要求。1億5000万ドル超の直接的資金援助を求める申請者の場合、施設従業員と建設作業員向けに児童ケアサービス提供計画提出も義務付けました。
「より大きなインパクト」では将来収益が上がった際には援助資金の一部償還が求められています。多額の公金が投入される以上、成功時の米国への利益還元を義務付けました。
第1弾の資金援助対象に含まれた「先端パッケージング施設の建設、拡張、現代化」について、半導体製造の後工程は労働集約的なため、人件費が高い米国で成功させることは難しいとの意見も聞きます。
日系企業には第1弾の対象先はなく、半導体材料及び装置分野に関連する第2弾資金援助対象です。第1弾対象企業がCHIP法を利用して投資を拡大すれば、日系の材料及び装置メーカーへの発注も増えるでしょう。
CHIPS法の成否はこれからですが、前述のガードレール条項は米中双方に拠点を構える企業に難しい経営判断を迫ります。制約の割に十分な投資奨励策とは言えないとの評価も聞きます。
CHIPS法の効果にかかわらず、先端半導体分野の脱中国シフトは進むでしょう。トランプ次期大統領は半導体のみならず、対中強硬姿勢を示しています。米国人の半導体保守サービスへの関与も既に禁止されており、米系企業は今後中国では先端半導体に投資をすることは表向きは困難と思われます。
その一方、前述のように大手メーカーが続々と米国内で先端半導体製造施設の建設に投資しています。米系を中心に脱中国の動きが加速し、日系材料・装置メーカーもグローバルな体制見直しを迫られそうです。
(了)